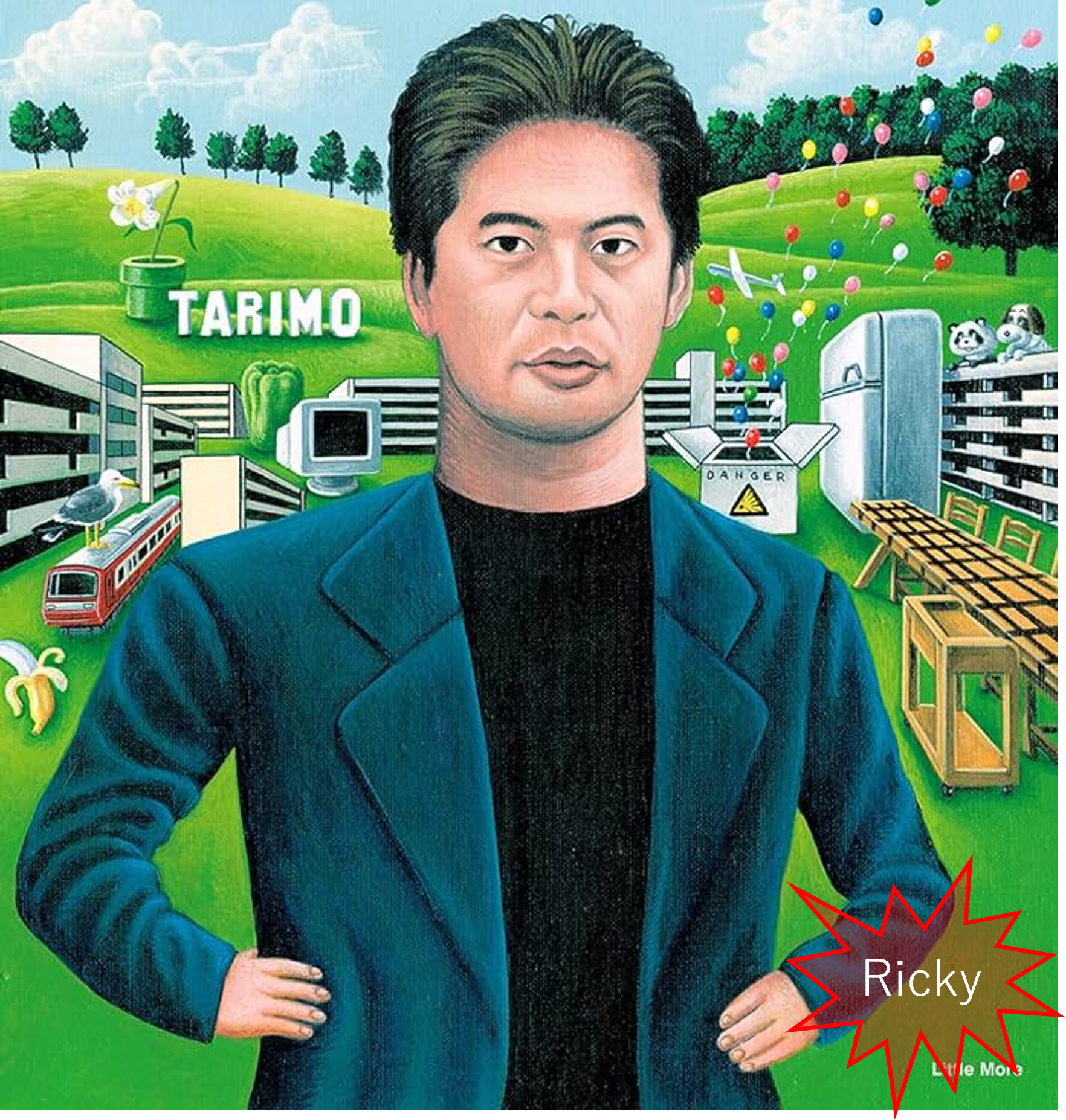とある映画の話をしたい。主人公は、鉄道を愛する青年、小町と小玉(新幹線の名前が由来となっている)。双方ともに、休日はもっぱら鉄道に乗って観光を楽しむ、気弱だが優しく、恋愛には奥手の、典型的なオタク気質の若者である。その二人が鉄道を通じて出会い、鉄道を中心に、仕事や恋愛が発展していく。紹介したいのは、その映画の中の、ひとつのシーンである。
主人公の小町が、オフィスに出社してくる。そこに、彼のことを好いている同僚の女性社員が駆け寄ってくる。そして彼に「良い物件が空いたわよ」とこっそり耳打ちする。彼らは不動産デベロッパーで、優良物件の動向に詳しいのだ。

小町はつい最近、住んでいたマンションの老朽化により住処を失っている状況だった。風景を楽しむタイプの鉄道オタクである彼は、地下鉄へのアクセスが便利なそのマンションには興味は示さない。そして、特に進展しないままその会話は終わり、二人はカメラの外へと歩き去っていく。なんてことのない、どこにでもある、平凡で、日常的な風景の1シーンだ。
しかし、そんなシーンにも拘わらず、観客は彼らのやり取りに途中からまるで集中できなくなる。なぜならそのやり取り背後で、あることが繰り広げられており、それに目を奪われてしまうからだ。
彼らの背後の、オフィスの玄関付近で、なにやら二人の男が揉めている。黒人の警備員が、クレーマーと思しき男を羽交い締めにし、オフィスからつまみ出そうとしている。双方の声は聞こえてこず、ただ業務的に、警備員はその体躯を生かして、クレーマー男を抱え上げ、追い出そうとしている。それが、先述の物件のやり取りと、同時並行で画面に収まっているのだから、異様である。いったい何を見せられているのだろうと、そのあまりに脈略の無い演出方法にも笑いつつ、我々は困惑してしまう。

こんな演出は、映画制作の教科書的には、絶対にご法度である。あるシーンを描く際には
「余計な情報は排除すること」が第一の原則として掲げられているはずであり、背景の小道具、エキストラ、照明、音楽、すべてがそのシーンのためだけに存在している必要がある。
無論その原則は、この作品にも適用されて然るべきだ。しかも先述の彼らの会話は、映画の今後の展開としてはそれなりに重要なシーンであり、本来であれば、観客には集中してそのやり取りを聞かせたいところのはずである。
しかしこの作品では、そうした原則をやすやすと破り、観客に正々堂々、違和感のカオスを提供している。森田芳光監督の『僕達急行 A列車で行こう』という映画である。
森田映画には、こうした演出が散見される。またそれが彼のオリジナリティであり、コメディ映画の大家として名を馳せるわけだが、私はこれまで、それが不思議で仕方なかった。他のコメディ映画のように、分かりやすいギャグ、逸脱行為などがあるわけではなく、あくまでも森田は、上述のような何気ない日常を描くだけである。ただその「据え置き方」が不思議なので、違和感となっており、そこを我々は笑ってしまう。
そもそも、この違和感を覚える理由とはなんだろう。
また、我々が笑ってしまうのは、こうした違和感だけが要因なのだろうか。
そして、森田はこの演出に、何を意図しているのだろうか。
今回はこの謎を解明していきたい。そのために、多少アクロバティックな方法ではあるが、文章表現の形態のひとつである「写生文」というものを、解明のツールとして採用してみようと思う。そしてまた、その「写生文」の概念に革新を施した、夏目漱石という稀代の作家の思想にも迫っていきたいと思う。
森田芳光の簡単紹介

森田 芳光(もりた よしみつ、1950年1月25日 – 2011年12月20日)は、日本の映画監督、脚本家。シリアスなドラマから喜劇、ブラックコメディー、アイドル映画、恋愛映画、ホラー映画、ミステリ映画と幅広いテーマを意欲的に取り扱い、話題作を数多く発表した。
1981年、若い落語家を主人公とした『の・ようなもの』を、実家を抵当に入れた借金で製作してデビュー。
1983年、松田優作主演の『家族ゲーム』を発表する。家庭をシニカルに、暴力的に描いた出色のブラックコメディーであり、何気無い日常の風景を非日常的に描写した、人を食った演出が評判となった。キネマ旬報ベストテン1位など同年の主要映画賞を多く受賞、一部の高評価にとどまっていた前作から大きく飛躍して、新世代の鬼才として広く注目を集める。
1984年、丸山健二原作、沢田研二主演の『ときめきに死す』を経て、薬師丸ひろ子主演の『メイン・テーマ』が大ヒットした。
1985年に、松田優作主演で、夏目漱石『それから』を映画化した。再びその年の主要映画賞を独占し、それまでの異色作路線とは異なって格調高い文芸大作であったこともあり、幅の広さを示して映画界での地位をさらに高めた。
1990年代前半は、映画の世界から少し離れ、シナリオ執筆や競馬エッセイの連載などの活動を優先。
1997年5月に、渡辺淳一『失楽園』を、役所広司、黒木瞳の主演で映画化した。人生に疲れた中年男女が不倫の果てに心中するというストーリーで、R-15指定を受ける。結果的に観客動員数が200万人を超える大ヒットとなり、「失楽園(する)」という言葉はこの年の流行語年間大賞にもなった。
そこからも精力的に作品発表を続け、2011年12月20日、C型肝炎による急性肝不全で死去した。61歳没。
森田映画の写生文的映画/夏目漱石との類似性
・『それから』に見る違和感と写生文

さて、様々なジャンルの映画を発表してきた森田であるが、その作品の特徴のひとつとしては、やはりその類稀なる「コメディセンス」があげられるだろう。特に、『の・ようなもの』『それから』『僕達急行 A列車で行こう』といった映画では、随所でそのセンスが光っている。しかしそれらは常に、分かりやすいギャグや、登場人物の大げさな逸脱行為といった種の笑いではないことは、前段で説明済みだ。
また一つ、具体的な例を挙げるとすれば、『それから』の1シーンだ。奇しくも原作は夏目漱石であるこの映画は、高等遊民である主人公の代助が、親友の妻を好きになってしまい、倫理観と愛情との狭間で板挟みになる物語である。抜粋するシーンは、その主人公が、また別の作家の友人からとある雑誌への執筆の依頼を受けているところである。

奥で会話している二人が、主人公と作家の友人である。蕎麦を食べながら、友人は代助に執筆を勧めるが、金に困っていない代助はそれをやんわりと断ってしまう。またここも、代助という、親から金銭的援助を受け、不労所得で生きる人間を、銭ゲバと化している友人と対比させることで、キャラクター付けしている重要なシーンだ。ただお気づきの通り、やはりこのシーンも、一筋縄ではいかなそうである。この手前の男性が、妙に視界に入ってくる。
たまたま近くに座っているだけのこの男は、その挙動から、おそらく噺家であることが伺える(噺家とは、江戸時代より伝統的に続く、【落語】という芸を披露する、いわばコメディアンのことである)。彼は二人の会話を盗み聞き、特に作家の友人の方の身振り手振りをマネする。落語は、座りながら上半身の動きだけで何人もの登場人物を演じ分ける芸なので、噺家にとってはこのように、修行の一環として、日頃から周囲の人間の挙動を模倣する、という行為自体は特に珍しいものではない。しかしそれが、主人公を差し置いて、画面の手前に映っているから、おかしい。後ろで重要な会話がなされているのに、我々観客は、どうしても手前の噺家の挙動に目がいってしまい、笑みがこぼれてしまう。森田お得意の演出である。しかし問題は、なぜこの演出が、そもそも違和感として映るのか、そしてなぜそれを、面白く感じられてしまうのか、である。
要因として、第一に考えられうるのは、先述の映画原則(余計な情報は排除すること)が、映画製作陣のみならず、一般大衆の中にも、あまりにも深く浸透していることが原因だと思われる。監督には、あるシーンを描く際に、そのシーンのメッセージを伝えるため以外の情報を極力削ぎ落すことが求められている一方で、また一般大衆は、そうした、既に「研磨された」映像以外を目にする機会がほとんど無いため、そこから逸脱した映像は、「違和感」として認識するのではないだろうか。たとえば、病に倒れた愛犬が死にゆくシーンを撮るとして、誰が、そのむせび泣く飼い主の後ろで流れる、エナジードリンクのテレビCMをカメラに映すだろうか。それがたとえリアルだったとしても、伝えたいメッセージと結びつかない情報は余計なものとして映り、それこそがつまり違和感の正体なのだろう。そしてそもそも人間とは、そこになにか「社会的逸脱」を見出すと、「笑い」というツールによって「是正」を試みる生き物である(「笑い」のメカニズムについてを、一からここで深堀りすると長くなってしまうので、それはまた別途ブログを書いてみることにする)。だからこそ、セオリーを無視したこの、「奥で話している二人を差し置いて、身振り手振りをする噺家を手前に置く」という演出方法に、笑いが込みあげるのだと思う。
しかし、果たして理由はそれだけだろうか。このシーンが笑えるのは、ただ「逸脱」しているからだけなのだろうか。森田映画の場合、答えは否だと、私は考える。このシーンが笑えるのは、この描写が多分に「写生文的だから」、というのが、もう一つの解に思えてならないのだ。しかしそれを説明する前にまず、「写生文」とはいったいなにか、を紐解いて行く必要がある。
・写生文とは

写生文とは、読んで字のごとく、文章表現における、文体の定義である。映画監督をテーマにとり上げておきながら、その魅力を伝えるにあたって文体の定義を持ち出すのは、一見おかしなことに思えるかもしれない。ひとまず、そもそもの写生文の一般的な解釈から見てみよう。写生文という言葉は、Wikipediaでは一応、下記のようなものを指すらしい。
写生によって物事をありのままに書こうとする文章。明治時代中期、西洋絵画由来の「写生」(スケッチ)の概念を応用して俳句・短歌の近代化を進めていた正岡子規が、同じ方法を散文にも当てはめて唱導したもので、子規・高浜虚子らを中心に発展し、近代的な日本語による散文の創出に大きな役割を担った。
なるほどつまり、目の前にある風景を、なるべくリアルに近い状態でキャンバスに写す「スケッチ」という言葉を、文章に置き換えたものが、「写生文」ということだ。たしかに、森田の映画は、まるでリアルに存在している風景が、たまたまカメラに収まったかのようなシーンが多々見受けられる。またそうしたごく自然な演出方法が、心を和ませ、多くのファンを癒している、というところも大いにある。
しかし、この「写生文」の理解だけだと、写生文映画とはつまり「リアルなものをただリアルに映しているだけのもの」となってしまう。この「写生文」の定義だけでは、なぜ森田映画が「違和感」そして「笑い」を生み出すのかが、不明瞭である。Wikipedia的な「写生文」の定義と、私の言う森田の「写生文的映画」の定義の間には、いまだ溝がある状態である。いったいこの溝、いかにして埋まるのか―
そう、そこで登場するのが、ほかならぬ夏目漱石という存在なのである。彼が「写生文」の概念を革新したことが、私に森田映画を「写生文的」と評させる他ならぬ要因なのである。
・夏目漱石と写生文

夏目漱石は活動初期、自身が執筆した評論文において、まさに『写生文』というタイトルにて、写生文について論じている。これを読むと、上記の定説とはまた少し違った角度から、写生文というものを見ていたことが分かる。下記に一部を抜粋する。
写生文とは、親が子供を見る態度である。<中略>
写生文家の描く所は、多く深刻なものでない。いかに深刻な事をかいても、この態度で押して行くから、ちょっと見ると底まで行かぬような心持ちがするのである。しかのみならずこの態度で世間人情の交渉を視るから、たいていの場合には滑稽の分子を含んだ表現となって、文章の上にあらわれて来る。
なるほどたしかに、大人たちが子供同士の喧嘩を見て微笑ましく思えてしまうのも、彼らの感情に同期することなく、俯瞰でそのやり取りを見ているからだろう。ぬいぐるみを取られた5歳児に感情移入して、泣いてしまう親がどこにいるだろうか。また、漱石の代表作である『吾輩は猫である』なぞは、その名の通り猫が主人公なのであるが、その猫の目線から描かれる人間の群青劇は、どこか高みからの見物といった感じで滑稽であった。
このように漱石は、写生文の定義を、「単なるスケッチ」ではなく、「高みの見物による、滑稽さの醸成」という定義に刷新した。そしてこの刷新を、おそらく森田は見逃さなかった。そうした漱石の哲学を自身の映画作りに取り入れ、「違和感」と「笑い」とを生み出す作風に至ったのではないか、と私は睨んでいる(漱石原作の映画化を監督しているのだから、あながち間違った推測でもないはずだ)。
さぁ長くなった。以上を踏まえたうえで、森田映画の例のシーンを、改めて分析していこう。
・森田映画における写生文的描写

前出の、『僕達急行 A列車で行こう』での、小町と女性社員のやり取りと、黒人警備員とクレーマー男との格闘とが、同時にカメラに収まっているシーンについて述べよう。
この画面内では、言うまでもなく、二つの物語が進行している。それを我々観客は、神の視点さながらに、「群青劇」として見ることが出来る。これがもし、たとえば、カメラが後ろの二人の格闘の描写にだけ、フォーカスしていたとしたら、事態はいったいどうなっていただろう。たぶん人によっては、膨れ上がる上腕二頭筋を持つ警備員の、忠誠心のこもった瞳に感情移入をし、「そんな不審者、はやく追い出してしまえ」と内心声援を送るかもしれないし、あるいは人によっては、額にあぶら汗をかくクレーマー男の方の悲しげな視線に同情し、「がんばれ負けるな」と唾を飲みながら見つめるのかもしれない。いずれにせよ、差し迫った彼らの表情から、その感情へと没入し、画面にのめりこむように はずだ。しかし森田はこの格闘の描写を、主人公たちの背後に据え置いてしまった。彼らのその表情、声は遮断され、往来するエキストラと同程度のサイズ感で映り込む、単なる風景の一つへと変貌した。そしてそのことにより、神の視点を手にしている私たち観客にとって彼らの白熱した格闘は、あっという間に「滑稽」なものとなってしまったのである。
しかし、これこそが「自然」ではないだろうか。人生における、あらゆる場面を振り返ってみても、同じことではないだろうか。その一つの空間の内には、なにか真剣になっている人もいれば、不真面目な人もいる。泣いている人もいれば、笑っている人もいる。そんな相反する状況がひと時に共存しうるのが、リアルである。それであるのに拘わらず、たとえば時にカメラなどというアイテムを持ち出して、狙った場所を意図的にフォーカスし、観客を狙い通りの感情へと誘導させる、といった行為は、森田、ひいては漱石からすると、むしろそっちの方がよっぽど不自然なのである。上述のような混交した空間こそが自然で、そして、このような自然を、遥かなる高みから見た時、人はそれが面白く、滑稽に感じるのだ。団地のベランダから洗濯物越しに見える、小学生の運動会が、微笑ましく感じる如くに。これこそが、森田映画の「違和感」と「笑い」にメカニズムの正体である。
おわりに…
またしても大好きな夏目漱石を持ち出してしまった。ところで彼に対する世間のイメージとは、神経衰弱で、利口で、気難しい人間、といったものである。おそらくそれもまた的外れというわけでもないのだろうが、しかし一方で、漱石という人間はやはり、この俗世で活動する人間たちが、煩悩にまみれた衆生たちが、愛おしくて仕方なかったのではないか、とも思う。虫の居所が悪いと妻であろうと弟子であろうと当たり散らし、また被害妄想が強く、周りの人が自分の悪口を言っているのではないかと気にするような偏屈な男は、他方では、そうした自分も含めた凡人の生活を、なるたけリアルな視点から「愛すべき滑稽なもの」として仔細に小説に書き起こすほど、博愛主義的人物でもあったのだ。
そんな彼だからこそ、登場させる愛すべき滑稽なキャラクター達を、少なくとも自分の作品の中では、決まった筋道に当て嵌めた、まるで将棋の駒の如くに描くことを避けたのではないか、と思う。それを証拠に、『写生文』ではまた、彼は下記のような言葉を残している。
筋とは何だ。世の中は筋のないものだ。筋のないもののうちに筋を立てて見たって始まらないじゃないか。
たぶん、森田も同じ気持ちで世を眺めていたのではないか、と思う。森田は晩年、『僕達急行 A列車で行こう』の続編を画策していたらしい。小町と小玉が、今度はまた別の土地で、例によって鉄道を中心とした群青劇を繰り広げる内容だったのだろうか。しかしその夢叶わず、彼はこの世を去ってしまった。61歳。惜しまれる死だった。まだまだこれからであったはずだ。おそらく森田という映像作家はまさにそこからが、噺家のように、老いれば老いるほど味わい深さが増す、円熟期になるところだったのだ。しかし、いくらそのような哀惜の言葉を吐いたとて、仕方ない。これは、一介の森田映画のファンとしての、自らにかける慰めの言葉である。多少不謹慎な表現になってしまうかもしれないが、彼は天国に行くことでようやく真の滑稽を手にした、とも捉えられるかもしれないのだ。彼の世とは、それこそまさに神なる視点である。彼の世に行くことで初めて、彼が求めていた本当の意味での「愛すべき滑稽なもの」たちの群青劇が、眼下に広がっているのではないだろうか。無論そこには既に、憧れの漱石先輩が、100年以上もの間飽きることなく、特等席を構えて座り続けているはずだ。できれば両者肩を並べ、我々の筋のない物語を、笑いながら、見守ってくれていてほしい。そんな不謹慎で勝手な妄想が、つい膨らんでしまう。

★このブログのライター:Ricky★
文化的なことならお任せを!ジャパニーズカルチャーの伝道師Rickyが、あなたを日本オタクに仕立て上げます!
出典
・森田芳光 Wikipedia
・写生文 Wikipedia
・http://books.salterrae.net/amizako/html2/sousekikokkeibungaku.html