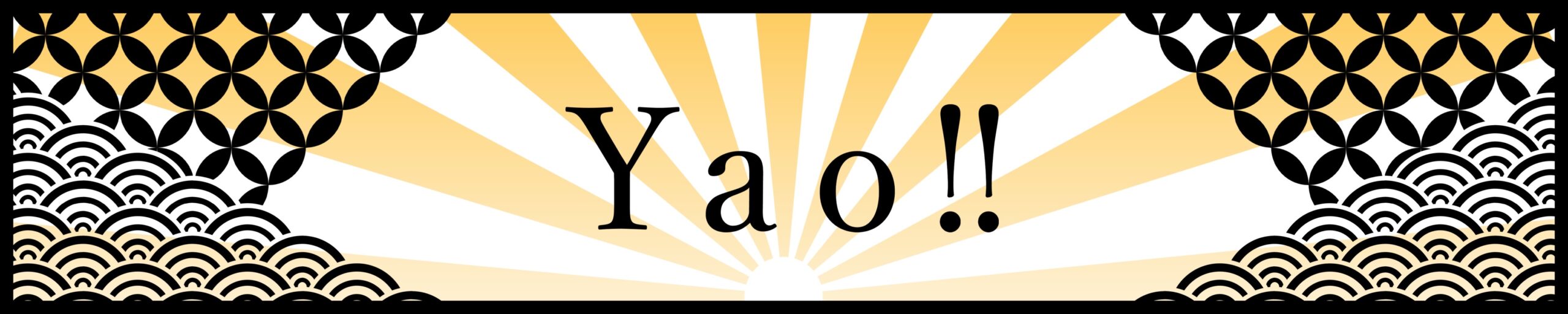東京の浅草にある浅草寺は多くの日本観光客や外国人観光客で賑わっています。
浅草寺にいくとその町並みや風景は日本文化をおおいに感じられることは間違いないでしょう。
ですが浅草寺がどのような建物で、どのような歴史があるのかをあなたは知っているでしょうか?
実は浅草寺の歴史は1400年近くあるのです。その昔から大切にされてきた浅草寺には一体どんな歴史があるのでしょうか。
浅草寺の歴史を知っておくことで、浅草を訪れた際により一層日本文化を感じ浅草観光を楽しむことができます。
日本人も浅草寺の歴史をよく知らない人が多いので、日本人より詳しくなってしまいましょう。
浅草寺の歴史

ご本尊の出現 飛鳥時代628年
浅草寺の歴史は1400年前からあります。
飛鳥時代の628年3月18日の早朝にご本尊が現れたと言われています。
ご本尊とは仏教系の各寺院や信徒の仏壇などにおいて最も重要視される信仰対象(物)のことです。
宮戸川(現在の隅田川)で檜前浜成・竹成兄弟が漁をしている時に投網の中にかかったのを見つけました。
網から逃がして、場所を変えて漁をしていても、何度もご本尊が網にかかったのです。
そのことから、兄弟は持ち帰り、土地の長にその像を見せました。
その像は観世音菩薩だと判明し、お堂に供養することにしました。
これが浅草寺の始まりだと言われています。
中興開山
中興開山とは、衰えていたものを、再び繁栄させることです。
645年に、とある僧が観音堂を修造しました。その僧はこれをとても大切にするように告げました。
平安初期になると、慈覚大師円仁さまがこの地を訪れました。慈覚大師円仁さまは浅草寺の中興開山をした人です。
そこから浅草の地は宗教的な地として次第に発展していったのです。
平安後期の地震と火災からの再建
そんな浅草寺ですが、1041年に起こった大地震により崩壊してしまいました。それをある修行僧が見て再建を志したのです。
そこから10年後の1051年、ついに再建が完了されました。
ですが1079年、原因不明の火災によって、浅草寺は焼けてしまいました。
1169年にある上人が再建を志し、浅草寺は再び再建されたのです。
源頼朝の参詣
鎌倉幕府の初代将軍である源頼朝もこの浅草寺に参詣したことで知られています。
源頼朝とは日本人なら一度は誰もが耳にしたことのある、日本の歴史上で有名な人です。
「浅草寺」という名前がこの寺に使われはじめたのは実はこの頃からなんです。これは鎌倉時代に編纂された歴史書『吾妻鏡』に記されているそう。
この浅草寺は日本の歴史的な武将である源頼朝が平家追討の際に訪れ、戦勝を祈願した場所なのです。
この時だけでなく、藤原氏征討の際にも浅草寺に土地を寄進したと言われています。
源頼朝の参詣や源平の戦いで武者たちの間でも浅草寺は次第に知れ渡り、多くの武者たちの信心が注がれるようになりました。
足利尊氏と武将たちからの庇護
足利尊氏といえば室町時代に15代にわたり中央政府に君臨し続けた足利将軍家の祖であり、室町幕府を開いた征夷大将軍です。
そんな足利尊氏も浅草寺と深い関わりを持っていました。
具体的には足利氏は浅草寺に参り寺領を安堵したり、再建、寄進などを行ったりしたとされています。
それ以外にも造営や修復も複数代にわたり続けていったそうなのです。
歴史上の有名人物である足利氏だけでなく、これもこれも有名な北条氏も浅草寺を祈願所としていました。
浅草寺運営の基盤を固めていったのも北条氏なのです。
天下統一を果たした徳川家康も武運を祈願
日本の歴史で最も人気のある戦国時代から江戸時代。
この時、織田信長のあとを次いで最終的に天下統一を果たした徳川家康を知っている人も多いでしょう。
そんな徳川家康も武運を祈願しに浅草寺を訪れていたのです。
先に源頼朝も浅草寺に参詣していたと話しました。
徳川家康は武家政治の創始者となった源頼朝を尊敬していたのです。
そんな源頼朝と深く関わりのあった浅草寺であることから、徳川家康も浅草寺を祈願所として選んでいたのです。
かの有名な関ヶ原の戦いの際も、祈祷を浅草寺で行ったのです。
関ヶ原の戦いという大きな戦いは徳川家康率いる東軍が勝ちました。その祈祷場所であった浅草寺の霊験は天下に一気に広がっていくことになったのです。
江戸時代の浅草寺

1625年に江戸の上野に寛永寺が建立されました。寛永寺は徳川幕府の安泰と平安を祈願するためのお寺です。
浅草寺は後に寛永寺の支配下に置かれ、幕末までその管理下にありました。
当時の仏教界最高権力であったのは輪王寺宮でした。輪王寺が統括するもののひとつとして浅草寺が含まれていました。ですので当時の仏教界最高権力下にあった浅草寺が、様々なものを享受できたことは言うまでもありません。
ですが江戸幕府にも財政難の時期がありました。その時には浅草寺の管理がよく行き届かなかったといいます。ですが人々からの信仰を集めていた浅草寺は、庶民の助けがあり存続しました。このことからより一層、庶民との繋がりも深くなったのです。
庶民文化の拠点
浅草は当時の中心地であったことからどんどん拡大していきます。
そして浅草寺を含む浅草は人との参詣や行楽、歓楽の場として盛り上がっていきました。
見世物小屋での興行は多くの参詣人を楽しませていたそうです。
これらの興行は江戸中の評判になったので、将軍や大名、仏教最高権力の輪王寺宮なども浅草の地を訪れ、興行をも楽しんだのだとか。
その様子は日本を代表する浮世絵師歌川広重も絵に残すほどのものでした。
明治時代。浅草寺の近代化
江戸幕末から明治への転換期、明治維新という革命が日本で起こりました。その時代の変化はもちろん浅草寺にまで影響を残します。
境内地が区画で整備されたり、見世物小屋も新たに作られた区へ移動させられました。
見世物小屋が移動した場所は盛り場として栄えていき、東京屈指の歓楽街が形成されていったのです。
見世物小屋がどれほどインパクトがあったものなのかが伝わりますね。
浅草の地には日本初のエレベーターを備えた展望塔も作られたことから、浅草という地は信仰のみならず、時代を先取る街として繁栄していきました。
浅草寺の力と復興
1649年に再建されて以降300年もの間、浅草寺の本堂は火事を免れてきました。
江戸時代の文献にも多くの霊験によって浅草寺は守られてきたと記されています。
関東大震災の際も、仲見世は全焼したが主要堂は奇跡的に火災から免れたそう。それでも第二次世界大戦の東京大空襲の際に崩壊してしまいました。
ですが天皇陛下、パナソニックの松下幸之助や複数の要人の寄進によって本堂、雷門、宝蔵院、五重塔などが再建されていきました。
最後に

どうだったでしょうか?
浅草寺が1400年もの歴史をもち、かつ誰もが知っているような日本の歴史人物とも深い関わりを持っているとは知らなかった人が多いと思います。
そしてここまで見てきておわかりの通り、多くの人々から信仰心を集め大切にされてきたのです。
国外国内から現在でも多くの観光客で賑わっている浅草寺は、きっとこれらの歴史的背景から人々を惹きつける魅力があるのでしょう。
皆さんも浅草寺を訪れる際はぜひこの歴史を振り返りながら観光してみてください。
参考サイト
【この記事を書いた人:よだとも/YodaTomo】