日本で一番有名な小説家と言えば、誰の名前が上がるだろうか。存命の作家ならば、村上春樹、東野圭吾、湊かなえ、ここら辺だろうか。亡くなっている人物なら、太宰治、芥川龍之介、三島由紀夫あたりか。国語の教科書にも名前が載るような彼らが今後、永世的に、その知名度を欲しいままにするのは間違いない。しかしそうは言っても、たとえば彼らが、日本紙幣の肖像として採用されることはあるか、と問われると、簡単には肯んじない。
最近だと、2019年に一万円札に渋沢栄一が選定されたことが日本銀行から発表された(発行は2024年)。また過去には、福沢諭吉、板垣退助、伊藤博文などが選定されている。つまり日本紙幣の肖像の採用基準としては、やはり上記メンバーのような、政治的、経済的な社会貢献を果たした人物が選定されるのだと思われる。
そう考えると、単なる一小説家だった夏目漱石が、1984年から2007年までの20年以上もの間、1000円札として選定されていたのは、異例の抜擢だったといえる。(同じ小説家として5000円札に選定された樋口一葉がいるが、彼女の場合は、当時の女性の社会進出の進展に配意された節があるので、ここでは除く)

何を言いたいのかと言うと、漱石が長きにわたり、使用頻度の最も高い1000円札として選ばれ続けてきたのはやはり、ひとえに、その文学的価値、知名度、によるものだったのではないか、ということだ。『吾輩は猫である』『坊ちゃん』『こころ』『三四郎』…
日本人なら誰でも知っている傑作を生みだし、国語の教科書はもちろんのこと、没後100年以上たってなお、彼の評論、研究論文は出版され続けている。(海外の認知度、となると、そこまで高くないようである。文学以外でも何かと話題性に富んだ三島などのほうが、よっぽど知られている)
彼の文学の求心力の正体は、いったい何なのだろうか。私は、それはもしかしたら、言文一致運動の渦中にあったのではないかと考えている。今回のブログでは、主にその正体を探る内容にしたい。
夏目漱石とは

1867年2月9日(慶応3年1月5日) – 1916年(大正5年)12月9日
日本の教師・小説家・評論家・英文学者・俳人。
帝国大学(のちの東京帝国大学、現在の東京大学)英文科卒業後、松山で愛媛県尋常中学校教師、熊本で第五高等学校教授などを務めたあと、イギリスへ留学。大ロンドンのカムデン区、ランベス区などに居住した。

帰国後は東京帝国大学講師として英文学を講じ、その職を辞した後、小説を書くようになる。神経症を患いながらも傑作を生みだし、朝日新聞社で小説記者を務めつつ1916年、胃潰瘍で50歳の若さで死去。その生涯において、小説執筆に 充てた期間はたったの10年だった。

夏目漱石とアイデンティティ
夏目漱石は、生まれてすぐ里親に出されている。父親の書生だった塩原昌之助夫婦のもとで彼は9歳までの年月を過ごした。長くの間、彼らを本当両親だと思い込んでいた(塩原夫妻もそのように嘘をついていた)。しかし、昌之助の不倫問題で実家に戻された際、女中に「この二人こそ実の両親である」と告げられたので、ようやく事態を把握したのである。幼心に、これがどれほど堪えたことだろう。また漱石は、8番目の子供ということもあり、生家に戻ったとて、実の父親である直克からの愛情は皆無に等しかった。たらい回しのようにされた挙句、何処にも居場所を見いだせなかった漱石少年。

「僕は必要とされているのだろうか。取り換え可能な存在なのだろうか」
気まぐれな大人たちの間で、弄ばれた思いだったに違いない。そうした人々の“恣意的な”姿勢への警戒心が幼心に育まれてしまった。
そんな中で彼は一体どのように、アイデンティティを獲得したのだろうか。むしろ、我々はふつう、アイデンティティをどのように、あるいはどこから得るのだろうか。やはり考えやすいのは、家族だろうか。実の両親に愛され育つことで、“家族の一員としての自分”というアイデンティティが、まずは育つのかもしれない。
しかし漱石の場合、その出発点で躓いてしまった。血縁とか、家庭環境とか、本来であれば確固たる礎のようなものが、彼からしてみればいずれも“恣意的”で、「取り換え可能」であった。むしろそうした“虚無”な状態にこそ、真のアイデンティティがあるのかもしれない、と考えた。
だから彼は、自身のアイデンティティを、“創作”の中に見出そうとしたのだ。彼にとって創作とは、単なる職業、趣味、そういったものを超越していた。
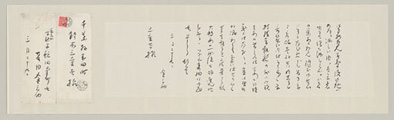
死ぬか生きるか、命のやりとりをする様な維新の志士の如き烈しい精神で文學をやって見たい。―明治39年10月26日付鈴木三重吉書簡
言文一致
話は変わるが、ここで今回のテーマ【言文一致】について、簡単な説明をしておく。
言文一致(げんぶんいっち)とは、日常に用いられる話し言葉に近い口語体を用いて文章を書くこと、もしくはその結果、口語体で書かれた文章のことを指す。
日本語を主要な言語とする日本では、明治時代に言文一致運動の高揚からそれまで用いられてきた文語文に代わって行われるようになった。大正末期には言文一致運動は完成したと考えられた。
「言文一致」は、現実をより写実的、透明に、直接的に書き出すことを目指していた。すなわち書き言葉は修辞上の道具であることをやめ、現実を映し出すための翻訳・コミュニケーションのツールとなる。直接目にされた風景も、目に見えたままに描写されることになった。すなわち、西洋哲学が導入・吸収されたことで、自然は科学、芸術を通じて客観化され、現代的な風景の概念と主観性が発見されたのだった。こうした発見は、様々な形式を持つ自然主義の人気を高めることになった。作家達は、伝統的な想像概念に基づいた優雅で遠回しな文体を離れ、個人的な視点を採用するとともに、少なくとも理論上は美化や誇張をせずに、自然の動きを捉えることに努めた。
とまぁ上記が教科書的な見解であるが、すなわち言文一致とは、明治維新による、西洋化を目指した運動の一環に過ぎないのである。

それまで日本は、「標準語」などという概念は存在しなかった。しかし西洋化を目論む明治政府は、中央集権の足掛かりとして「東京語標準語化計画」を発足し、これを半強制的に全国へ布教させた。
また当時、書き言葉と話し言葉は、断絶されていた。それまで文章は、形式主義的で、修辞としてのツールであり、同時に漢字中心であった。たとえば「大河」という漢字は、「たいが」とも「おおかわ」とも読める。二つは意味が異なるもので、つまり読み手次第で、文字の解釈が違ってくるのだ。こうした一部分をとっても、文章表現の取り換え可能な構造および多様性がうかがい知れる。
しかし言文一致運動により文章は、「気持ちの表明」に成り替わりつつあった。つまり、文章=感情という図式が生まれた。漢字ではなくひらがな中心になり、文章が、取り換え不可能なものに変貌してしまったのだ。たとえば現代では、スマートフォンのメッセージアプリに代表されるように、その文章のほとんどは口語である。「マジでヤバい」といった、ひらがなに頼った、感情が直結した文章になってはいやしないだろうか。
漱石の戦い・『吾輩は猫である』の特異性
- 漱石の戦い

漱石が生まれ、文学に触れたのは、まさにこうした言文一致運動の転換期だった。「見たままを、そのまま写実的に描く」といった自然主義的文学が台頭し、むしろそれこそが本来の文章表現であるかのように、歴史が改竄されようとされていた。
しかし、文部省の特派員としてイギリスにて英文学を、ひいては世界の文学の成り立ちを学んできた漱石は、そうした言葉の“恣意性”に警戒心を抱いていた。文学とは、本来「取り換え可能」なものであるべきだと考えた。文とは、状況や感情の直結とした表現手段ではなく、もっと多義的なものである。
ここで、その漱石の思想が最も色濃く反映されたと思われる、『吾輩は猫である』を紐解いていこう。
- 『吾輩は猫である』考察
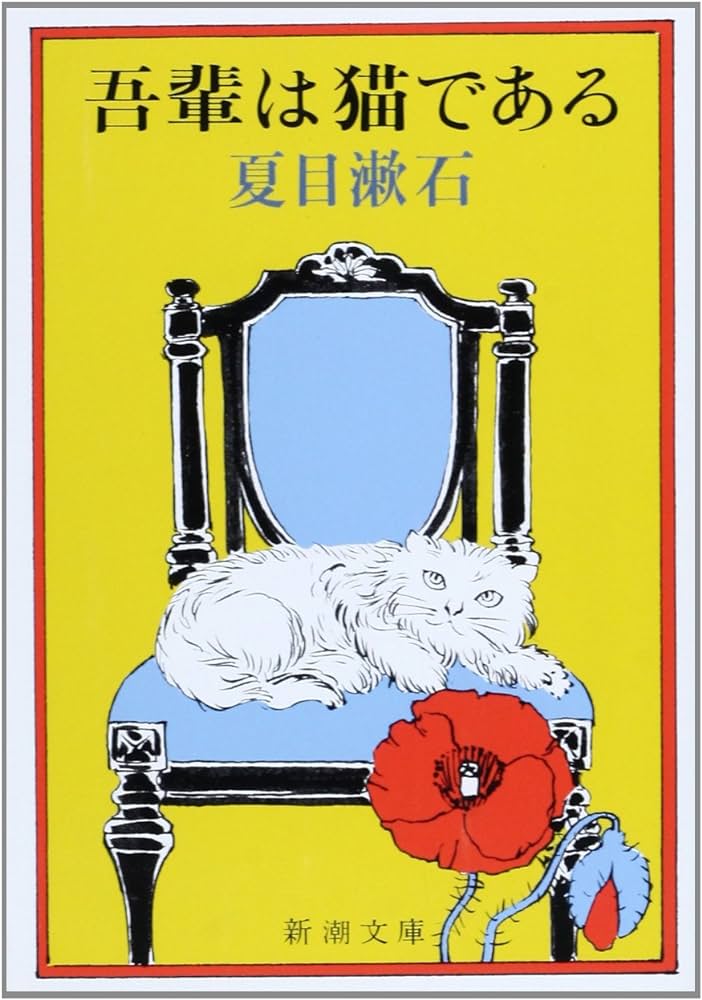
この作品は、「吾輩」と名乗る猫による一人称代名詞の語りによって進められること、つまり動物の猫を視点、動物(人物)とし、同時に語り手として作品が構成されている点が作品的特性であるといえる。語り手の一人称代名詞の「吾輩」そのものが作品の特性の一部となっている。この一人称は同じ激石の作品中でもきわめて特異なものだといってよい。視点動物の「猫」が、一般的な人間優位の立場とは逆に、人間世界の様態を観察するという構図になっている。つまり、写し出す主体は「吾輩」の猫、写し出される客体は人間そのものである。特に、「吾輩」の猫による飼い主の日常生活の滑稽なパターン化は、「見たままを模写する」という自然主義的文学を基軸としながら、部外者の立場にたって上から見下ろすという視点、の下に人間の優位性を逆転するという語りなのである。『吾輩は猫である』の「吾輩」はそうした複雑な背景を持つ語りの上に構築された一人称だと考えられる。

また同時にこの作品は、日本語ならではのニュアンスをもっている。これは日本語の複雑なところであると同時に、日本語の優越性でもある。同じ漢字を使う中国語では、「吾輩」という言い方があるが、日本語のような尊大さのニュアンスがない。中国語の『辞源」、「辞海』、
『現代漢語調典』で「吾輩」の意味を調べようとしても『辞源』と『辞海』には「吾輩」が載っていない。『現代漢語詞典』には、一人称代名詞として用いる、という意味しかないのである。『吾輩は猫である』の中国語訳本は『我是猫』で、中性的な一人称代名詞「我」が使われている。それで、中国における『吾輩は猫である』についての研究は、猫視点の独自性を研究する場合においても、「吾輩」という一人称代名調の特性はほとんど見逃されている。
つまり、日本における漢字表現の中には、それが一文字であっても、いくつもの意味が眠っているのだ。単なる感情の発露として媒介ではなく、常に取り換え可能な、ある種の概念として存在している。
おわりに
自身が取り換え可能な子供だった漱石。
最後に、漱石の自伝的小説ともいわれる、『硝子戸の中』より、名文と名高い箇所を抜粋して終わりとしよう。
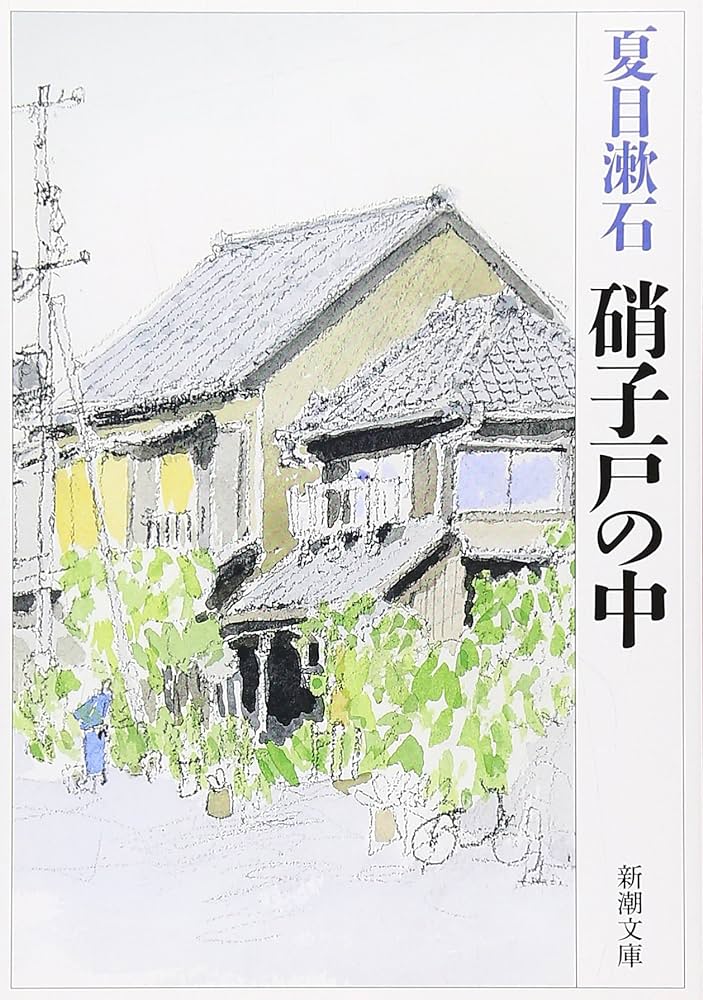
私の身の上を語る時分には、かえって比較的自由な空気の中に呼吸する事ができた。それでも私はまだ私に対して全く色気を取り除き得る程度に達していなかった。嘘うそを吐ついて世間を欺あざむくほどの衒気げんきがないにしても、もっと卑いやしい所、もっと悪い所、もっと面目を失するような自分の欠点を、つい発表しずにしまった。聖オーガスチンの懺悔ざんげ、ルソーの懺悔、オピアムイーターの懺悔、――それをいくら辿たどって行っても、本当の事実は人間の力で叙述できるはずがないと誰かが云った事がある。
まして私の書いたものは懺悔ではない。私の罪は、――もしそれを罪と云い得るならば、――すこぶる明るいところからばかり写されていただろう。そこに或人は一種の不快を感ずるかも知れない。しかし私自身は今その不快の上に跨またがって、一般の人類をひろく見渡しながら微笑しているのである。今までつまらない事を書いた自分をも、同じ眼で見渡して、あたかもそれが他人であったかの感を抱いだきつつ、やはり微笑しているのである。
ここにこそ、漱石文学の悲しみ、諧謔、滑稽、そのすべてが詰まっている。
その人の真実の姿なぞは、本来描写などできないはずだ、と漱石は言い切る。描いても描いても、恣意性の海に飲まれ、待つのは虚無だけだと知っていたからである。
しかし彼は創作を辞められなかった。そこだけに、アイデンティティのヒントを見いだせたのだろう。それはすこぶる不快の伴う作業だった。自分が取り換え可能であったことを、頼まれてもいないのに、わざわざ証明しようとした。またそれは同時に、時世の言文一致への反逆でもあったので、世間の風当たりも強かったはずだ。
だけれど彼はその時の自分の様子を、「ひろく見渡しながら微笑している」と表している。私はこれを、漱石の強がりのように思えてならない。自身の人生を、滑稽なものだった、と積極的に揶揄することで、むしろ防護しているのだ。私はそんな漱石の文学がとにかく愛おしい。お札の顔を拝むことは難しくなったけれど、彼の数々の名文は、永遠と人々の胸に残り続けるであろう。特に、自らのアイデンティティを見失いそうになった人には、慈しみを持った言葉で語りかけてくれるはずだ。

出典
・夏目漱石Wikipedia

・漱石論集成(柄谷行人)
・明治期日本文学における一人称の変遷(秦楽楽)
・『硝子戸の中』(夏目漱石)



